


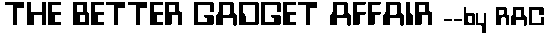
ナポレオンは、毒でもついているかのように手の中からカフリンクを放り出した。
「こいつは役に立たない」
「あんたの文句を聞いている時間はないんだ、ソロ」
ナポレオンは歯噛みした。
「まあ聞けよロバート、あんたがこの道具を渡して、これは相当なもんだと説明した時、僕はこいつがあんたの言った通りの働きをしてくれるものと考えた、それが、」
ナポレオンには研究部門長のロバートに何が起こったのか理解できなかった。ロバートは極めて友好的な男というわけでも、あらゆる基準からみて天才的というわけでもなかったが、一年前に昇進してからというものの、彼の態度は酷くなる一方だった。
するとロバートが、皮肉を殆ど隠しもせずに言い返してきた。
「あんた以外の者にはこれが常に正常に働いてるというのもおかしな話じゃないか。こいつが思う基準とやらに達してないと、ここへ私に文句を言いに来たのはあんただけだぞ」
「それこそ信じられないね」
「そうかね、じゃあ誰にでも泣き付きに行けばいい。私はウェイバリーに、ロンドンからえらいお荷物を引き受けさせられてるんだ。だがなんだって、あっちで片づけられない忌々しい役目が私のところへ降りかかってくるんだ!」
彼は肩ごしにぐいと親指を向け、嘲りの口調で言った。
「新入りの所へ行ってこい。アカ(共産主義者)の野郎にさ
彼はウェイバリー氏が、まさにU.N.C.L.E.の心臓部に敵側の人間を雇い入れたことへの不満を口にすると、ナポレオンのことは完全に無視して自分の仕事に戻っていった。
ナポレオンは無視されるのが気に入らなかった。何もかもが気に入らなかったが、諍っても勝ち目のないことも分っていた。この愚か者に対して、自分はウェイバリー氏の直接の命令が無ければこれ以上何も要求できないのだ。
彼はここでロバートを一発撃ってやればさぞすっきりするだろうなとしばらく物思いに耽っていたが、そこまでする価値もないと諦めた。
通路に出ると、隣の研究室に新しいネームプレートが上がっているのがすぐ目に入った。ナポレオンは打ち出しされた文字を指でなぞった。イリヤ・ニコヴィッチ・クリヤキン博士。
ああ、と彼は考えた。ロバートの言っていた『アカ』か。
ナポレオンが窓から覗いてみると、男が一人顕微鏡を覗いているのが見えた。彼の方から見えるのは、ブロンドの髪と白衣の下の黒っぽい服装だけだった。ドアをスライドさせ、ナポレオンは中に入った。
「ちょっといいかな?」
男は顔を上げた。青い瞳がじいっと見詰めてきて、ほんのしばらくナポレオンの注意を奪った。
「何だ?」
相手が噛み付くように言った。大歓迎されているような口振りではなかったが、ナポレオンは先を続けた。
「ドクター・クリヤキンを探してるんだが」
「もう会ってる」
ナポレオンは目を見張った。この男は博士号を取得しているような年頃にはとても思えない。けれどかろうじてそのことに言及するのはやめた。ナポレオンはカフリンクを取り出した。
「こいつに不満があってね」
ブロンドの男はカフリンクをちらっと見ると、ナポレオンを眺め回し、彼のネクタイから値の張る靴に至るまでの服装を検分した。そして顕微鏡に向かい直した。
「ならデザイナーの所へ持って行けばいいだろう」
ナポレオンは鼻を鳴らした。
「こいつは爆弾になるんだよ」
それで男は興味を示した。カフリンクをナポレオンの手から拾い上げ、目の前でためつすがめつしている。
「君の不満というのは何だい?」
「一度水に浸かると役に立たなくなる」
「それじゃ、爆破工作する前にひと泳ぎしようと思わないことだな」
その青い目に冗談っぽい光が瞬くのを見た刹那、ナポレオンはすぐにもぴしりと言い返してやるつもりでいた。しかし思わずニヤリとさせられてしまい、それから皮肉っぽい微笑みに変えた。
「それはどうも。十分考慮に入れておくことにしよう」
彼は手を差し出した。
「ナポレオン・ソロだ」
その手は強く握り返された。
「イリヤ・ニコヴィッチ・クリヤキン」
自己紹介が終わり、カフリンクはカウンターの上に置かれ、そしてイリヤはまた顕微鏡に向かった。ナポレオンは再び無視されているように感じ、このブロンドの男への好印象は薄らぎはじめた。
「今すぐ直してくれないか?」
イリヤがじろりと睨んだ。
「今すぐ必要なのか?」
いやそういう訳ではない。しかしそれはさほど問題ではない。
「そうだ」
「いや、違うだろ」
ナポレオンは眉を顰めた。
「何でわかるんだ?」
「それはもしあんたが『今すぐ』爆弾が必要だってんなら、今頃こんな話はしてないだろうからさ」
少しの間呆気に取られて、ナポレオンはがくんと膝を崩した。そしてどうにか言い返した。
「それなら、明日までに必要だと言い換えるよ」
イリヤは彼を不審げな視線でちらりと見たが、それでも頷いた。
「いいだろう。明日までにやっておく」
ナポレオンは相手がカフリンクを手に取り、何か始めるのを待った。しかし彼はまた顕微鏡を覗きだした。
ナポレオンは誰か真面目に取合ってくれて、外の世界では自分は殴られたり撃たれたり拷問されたりしていて、それが幾らか価値のあることなんだと分ってくれる者が欲しいとつくづく思った。
「君は調べてみもしてないじゃないか」
イリヤは溜め息をついたが、顕微鏡から目を離しはしなかった。
「その執念深い詮索癖からみれば、君がスパイなのも理解できるな」
ナポレオンはタタン、と一度カウンターを指で弾き、この男の襟首を掴んで捩じ上げるのは、明日カフリンクが間違いなく目下ここに置かれている場所に置きっぱなしになっているのを確認するまで待つことにした。
彼は一言も無しに研究室を出て、自分のオフィスに戻り、大成功とは言えない任務についてのレポートを書き上げた。そこにはカフリンクが作動しなかったことを大きく取り上げておいた。
ナポレオンは、ウェイバリー氏から新しい任務のため一時間以内に出発しろとの急な命令を受けて、あくる朝予定より早い時間にラボを再訪した。彼は寝不足で、その上自分がトロピカル・パラダイスなどとは正反対の場所に行かされることになり、今夜のキャンディとのデートも無しにしなければならなくなった事実に苛々しており、あの新入りにそのお裾分けをしてやるつもりでいた。
ラボに乗り込むと、思っていた通りカフリンクがまだカウンターに置いてあるのが目に入った。そしてクリヤキンは、いけしゃあしゃあとろくでもない顕微鏡をまだ覗いていた。
ちょっとの間、ナポレオンは相手が寝る時もこうしているんだろうかと考えた。彼は、誰が勝者なのかはっきりさせるための言い争いになるのに備えつつ、静かにどころでない勢いでカウンターをバンと叩いた。
「出来たのか?!」
「ああ」
いきなり毒気を抜かれ、ナポレオンは眉を上げた。
「出来たって?」
イリヤは顕微鏡から顔を上げた。ナポレオンはそれを覗いてみたい誘惑に駆られた。あのスライドの上は、マイクロスコープサイズの『ヒミツの覗き部屋
「君は今日までにこれが必要だって言った。そうじゃないか?」
確かに言ったが、本当にそうなるとは思ってもみなかったのだ。ここ最近、ラボの人間は誰も彼が必要な時に何かしてくれたことがなかった。いつも彼が戻ってきて、腕を吊っていたり顔に痣を作ってから何かを届けてよこすのだ。ロバートの態度は伝染病のごとく、皆を蝕ばんでいるようだった。
この男が頼んだ通りのことをしてくれたのは結構なことであるが、ナポレオンは言葉を失ってしまった。向かってくる堅いサンドバッグにパンチを繰り出すつもりでいて、代わりにゼリーの中にふんわり落っことされたような気分だった。彼は急き込んで言った。
「防水仕様になったのか?」
彼は疑い深げにカフリンクを睨み付けた。どうせまたいい加減なものに決まっているのだ。イリヤはカフリンクを取り上げて、カウンターの上に置いた。
「激流の中では持たないけど、噴水に浸かったぐらいなら大丈夫さ」
ナポレオンは目を細めた。それこそ正に自分に起こったことだった。THRUSHの構成員と取っ組み合っているさなか、彼は噴水の中に投げ込まれて、そして周りを取り巻かれてしまった。自由を取り戻すのに予想外に時間がかかったのは、まぬけなカフリンクが機能不全を決め込んでしまったせいである。
彼は細めた目の間から相手を睨んだ。
「どうしてそれを知っているんだ?」
青い瞳がきらりと光った。
「たまたま。当てずっぽうさ」
ナポレオンは眉を顰めた。相手が噴水の件を知る唯一の方法は、ナポレオンの報告書を読んでいることで、それは機密事項に属している。彼は口を開いてこの男に質問しようとしたが、相手の次の説明で脇に逸らされてしまった。
「これの仕組みを変えたんだが」
あああ――ナポレオンは思った。ほらおいでなすった。何かひっかけがあるのは分っていたのだ。
「どういう意味だい?」
彼にそれに付き合っている時間はなかった。
「僕にはこれがあまり実用的に見えなかった。君が要ると言ったのは、カフリンクが一対で爆弾になったもので、一方が爆薬、一方が起爆剤になっている。そうだろう?」
ナポレオンは頷いた。全くそのとおりで、全く苛々させられる代物だった。手を縛られている時に、両方のカフリンクを外すのは大層時間がかかるのだ。イリヤが続けた。
「爆弾として使うなら、手に届きやすくて、出来る限り操作が少ないものが必要だろうと思って、」
彼はカフリンクを持ち上げた。
「だから、今度のはひとつひとつが爆薬と起爆剤を兼ね備えている。ほら」
どれだけ簡単に扱えるかを示すため、彼は片方の手を使い、小指と薬指で下の部分を掴むと、カフリンクを親指の付け根に当て、それから親指と人差し指で頭の部分を三度捻った。
そしてカフリンクを持ち上げ、ナポレオンに発火の仕組みを見せた。
「こいつをカチっと音がするまで押す、こんな風に」
彼が指に力を入れると、中の機械が合わさってカチリと鳴った。
「そうしたら十秒待って、吹き飛ばしたい場所に投げるといい。爆発の威力は以前のものと同じだ」
ナポレオンは心の中で十秒のカウントダウンを始め、ゼロに近づくに従い少々の不安を募らせていった。
「あ―――…」
また片手を使って、イリヤは仕掛けを半回転させ、掌に返した。
「で、こうすれば解除される」
ナポレオンは仰天した。かつてラボの連中は新しい装置
それが、この男は一日と経たないうちに彼の不満を聞き、修理をし、その上何も言われずに更に改良を加えたのだ。
ナポレオンは外でこれを試すような状況になることを願ってしまいそうになった。彼はイリヤににんまりと笑いかけた。
「ありがとう」
そしてカフリンクを袖口に通し始めた。
「まだ礼を言うのは早い。それは試作品なんだ」
「それだってさ」
彼はカフスを留めると、上着の袖を伸ばした。
イリヤはからかうような笑いを浮かべた。
「君が神経質になって、そのカフリンクをいじくりまわしたりしないことを祈るよ、ミスタ・ソロ。うっかり君が自分の手を吹き飛ばしたなんてのは御免だから」
ナポレオンは相手をねめつけた。
「僕は神経質になんてならないよ」
「きちんとした身なりに鋼鉄の意志。世界の運命はしっかり守られてるってことだな」
そして時計を指で軽く叩いた。
「行った方がいいんじゃないか?」
ナポレオンはまた目を眇めた。
「どうしてそれを知ってるんだ?」
イリヤは答えなかった。
「役に立ったかどうか教えてくれ。君が自分を吹き飛ばしたりしなかったら、だけど」
イリヤは彼を戸口まで送って行った。ナポレオンはどうしてだか、言うなりに外に追い出されてしまっていた。
「もし僕が吹き飛んだら、それは君の失態だぜ」
「もちろん責任は全て僕が取るとも。さあさあ行ってくれ、頼むから」
気が付けばナポレオンはラボの扉の向うに出ていた。振り向いて窓から覗くと、イリヤはまた顕微鏡に向かっている。
ナポレオンはクスリと笑いを漏らし、袖口を眺めて、何かに守られているような、ほんわかとした妙な気分を味わった。それからもう時間が迫っているのを思い出し、スーツケースを抱えタクシーで空港へ向かった。
そしてそれは役に立った。とても信じられなかったが巧くいったのだ。その上水に濡れた後で。これはまったく驚きだった。
ナポレオンは自分のアパートに帰ってくると、生きて戻れたことをもう一度有り難く思った。そして今回は、あのロシア人のお陰なのである。
愉快で皮肉な巡り合わせにふふんと笑って、彼はバーコーナーへ向かった。ボトルを幾つか脇へ押しやり、未開封のままのストリチナヤを引っ張り出した。
そして自分のグラスに注ぐと、そこにはいない素晴らしきドクター・クリヤキンに向けて乾杯した。
翌日、ナポレオンはラボへと降りていった。イリヤの研究室のドアを開けると、ロバートがいるのを見て眉を寄せた。
「クリヤキンはどこだい?」
彼が誰より会いたくないのがロバートだった。
「何で聞く?あのアカが今度は何をした?」
ナポレオンは長い溜め息をついた。
「ロバート、僕に絡むのはよせ。彼がどこにいるか教えてくれさえすればいいんだ」
「どこかで人知れず土に埋められてりゃ有り難いな」
相手にするべきでないのは分っていた。ロバートと争って言い負かすのは不可能なのだ。この男は理屈に合おうが合うまいが、ひたすら自分の信条にしがみついている。まるでお気に入りの骨を咥えて離さないブルドッグのように。
しかしこんなことを言わせておくことは出来なかった。ナポレオンはロバートの胸を指で突いた。
「お前の言うところの『アカ』はね、お前よりずっといい仕事をしてるんだよ。さあ頼むから彼の居場所を教えて、それからとっとと自分のラボに戻るといい」
「――僕ならここに居る」
ナポレオンが振り向くと、イリヤが戸口に立っていた。ロバートはその隙にナポレオンから離れて出口に向かった。イリヤがゆっくりと道を開け、すれ違いざまに相手は呟いた。
「ふん、アカ野郎の肩なんぞ持ちやがって
イリヤに代ってナポレオンはむかっ腹を立てた。そして彼に強張った笑いを向けると、言った。
「全く面白い奴だよ。僕がパーティを開くなら真っ先に奴をご招待して差し上げたいね」
イリヤはカウンターに向かい、何か確かめるように顕微鏡に手を触れた。
「彼には神経質になってカフリンクをいじる癖はないのかな?彼個人用に一揃い作ってやれるのに」
ナポレオンは声を上げて笑った。イリヤの唇は半分だけ笑みの形を作った。
「君の方は、どうにか自分の手を吹き飛ばさずに済んだみたいだな」
イリヤの指は顕微鏡の横に置いてある書類を触り、また明らかに実験途中と思われる、他のカウンターの上の物品をちらちらと見遣った。ナポレオンはその様子を見ていて、すぐ彼が何をしているのか察しをつけた。
「奴が何かに触った様子はなかったよ。ちょうど何か探りに来たばかりのようだった」
イリヤが頷いた。そしてナポレオンに苦笑いを向けた。
「あんな風に僕を庇ったりすると、あんたまで彼を敵に回すことになるのに」
その言葉の中に感謝が隠されているのが分かって、ナポレオンは顕微鏡が置いてあるカウンターに寄りかかった。
「これまで奴の役に立たない装置で危うく殺されそうになってきたのを思えば、奴が敵に回ったところでどうってことはないさ」
彼は微笑みを浮かべた。
「ときに、どうもありがとう。このカフリンクはすごく役に立ったよ」
そこでロシア人は満足げに頷いた。
「そりゃあよかった」
彼は引き出しを開けて、新しい一対を取り出した。
「ほらこれ」
ナポレオンは喜んでそれを受け取った。コミュニケーターが鳴り出し、彼はスーツのポケットから機械を引っ張り出した。
「こちら、ソロ」
「おおソロ君、」
ウェイバリー氏からだった。
「君の報告書はまだ出来んのかね?」
ナポレオンはこっそりと溜め息をついた。
「一時間以内に提出します」
「それは結構」
ナポレオンはコミュニケーターを面白くなさそうに睨み、しまい込んだ。彼はイリヤに哀れっぽく笑みかけた。
「スパイの生活は刺激でいっぱいさ」
「君はその最たるもんだろう、ミスタ・ソロ。任務がお呼びだ」
「ナポレオン。僕のことはナポレオンと呼んでくれ」
自分の申し出が引き出した、ロシア人のはにかむような笑みは魅力的だった。ナポレオンはここを離れるのが惜しくなってきた。
「ここには書類仕事を片づけてくれるような何かいいものは無いのかい?」
イリヤはナポレオンの手にあるカフリンクを指差した。
「ひとつファイルめがけて投げつけてやればいい。そうすれば確実に必要なくなる」
「あーなるほど。そしたら僕は留置所に放り込まれちまうよ」
「書類仕事をしなくて済むチャンスじゃないか。そこに入ってる間は」
「そりゃどうも。でもその提案はご遠慮させていただくよ、ドクター。大人しく帰ってレポートを完成させることにする」
「お好きなように」
イリヤはまたはにかむように微笑んだ。
「……それと僕のことはイリヤでいい。君がそうしたければ」
自分でも説明のつかない理由で、ナポレオンの胸がどきんと鳴った。彼はイリヤに笑いかけるとラボを後にした。
五日後に任務を終えて、ナポレオンはまたイリヤに出くわした。
ナポレオンは人里離れた場所の打ち捨てられた納屋で、丸二日間縛られたまま何も食べられずにいた分を取り返そうと、カフェテリアで昼食を取るところだった。山のように積んだトレイを手にテーブルにつこうとした時、ぶつぶついう声が耳に届いた。二言三言聞いただけで、喋っているのがロバートだと判った。
「誰かがあのアカの野郎を追い返さなきゃならんのだ。ここじゃあいつに何の用もないんだからな」
ナポレオンが振り向くと、ちょうどイリヤがカフェテリアに入ろうとしているのが目に入った。ぶつぶつ声はまだ続いている。
「――ここにああいう奴等はいない方がいいんだ」
ロバートの態度はナポレオンをかっとさせ、こんな男に他の者が影響されてはならないと決心した。彼は声を上げた。
「イリヤ!」
イリヤは声のした方を見、少し置いて眉を上げた。
「ここで一緒に食べないか?」
ナポレオンは後ろのテーブルを指差した。イリヤの視線がロバートを捉え、少しの間彼は躊躇っていた。ナポレオンは彼が向きを変えて出ていってしまうのではと思ったが、幸いにもそれからイリヤは小さく笑ってこっくり頷くと、自分の食事を取りに行った。
ナポレオンはロバートの肩を、目的が分るようにぐいっと掴んだ。
「こんなことは止せ。とにかく止めろ。彼は僕たちと同様にここで働いていて、ここにいる皆がひとつのチームの筈だ」
ナポレオンは数人の目がこちらを向いていることを感じ、自分の言うことに彼らが耳を傾けてくれることを祈った。だがロバートは自分の周りを似た考えの者で固めているような疑いをも抱いた。
イリヤは奥のテーブルに向かって歩き出しており、ナポレオンはロバートを警告するように睨みつけると、ロシア人のところへ行った。
二人が落ち着くまでしばらく気詰まりな間があった。ようやくナポレオンは、はっきりと口に出すことにした。
「あの男は差別と偏見で凝り固まってるんだ。やつの言うことなんか誰も聞きゃしないよ」
イリヤが小さく微笑んだ。ほんの一瞬だけ。
「でも少しだけど同調者はいる」
ナポレオンは手を伸ばし、イリヤの腕に触れた。
「ま、この僕は同調なんぞしないさ」
軽く触れてくる手をイリヤは見下ろし、眉を寄せた。ナポレオンがその視線を辿ると、自分の手首にロープの擦り傷がついているのが目に入った。彼は手をひっこめ、袖口を引き下げて傷を隠した。そしてイリヤに皮肉っぽく笑ってみせた。
「任務のお土産だよ」
イリヤは口を開き、首を横に傾げた。
「君はいつも後ろ手に縛られるの?それとも前に?」
ナポレオンは少しの間考え、手をちょっと前に出してみたり後ろにしてみたりして、ここ数度縛られた時のことを回想してみた。
「両方、だと思うな。時には頭の上でとか」
彼は苦虫を噛み潰したような顔をした。
「あれは嫌なもんだな。自分じゃ何の防御も出来なくてさ」
そして眉をぴくぴくと動かした。
「でも何故だい?新しい装置を発明してくれるつもり?」
「気が向いたら」
「そりゃあいい。もうすぐロバートに命を任せなくてもよくなるわけだ」
イリヤは一瞬だけ、心からの笑みを向けた。それはナポレオンに、こんな笑みをもっと見たいと思わせるには十分な時間だった。
「あの男を殺して欲しい?」
ナポレオンはふんと鼻を鳴らした。
「やって頂けるのかい?」
イリヤが頷いた。
「ご用命とあらば」
「あっはっは」
ナポレオンは笑ったあとで、イリヤの顔つきをじっと見た。彼はもう一度イリヤの腕に触れた。
「冗談さ。君だってそのつもり、だろ?」
イリヤはがっかりしたようだった。
「世の中のためにいいことをしようと思ったのに」
「分かるけど、そしたら君は国外追放されてしまうだろう?じゃあ誰が僕のバクダンつきカフリンクを作るんだい。二人してロバートの奴に我慢しなきゃいけなかろうが、僕は君に居てもらう方がいいな」
イリヤは溜め息をついた。
「わかったよ」
ナポレオンはイリヤの瞳を覗き込み、そこに悪戯っぽい光が瞬いているのを認めてひと安心した。このロシア人のユーモアのセンスについていこうとするのは大変だということがよく分かったし、またそうなりたいと思っている自分にも気がついた。
次の任務で、ナポレオンはまたもや縛り上げられており、幾つかの理由から彼はなんとなくイリヤに思いを馳せていた。理由のひとつは頭の上で両手を縛られていたことで、それがどんなに嫌なものかこの前考えたのはイリヤといた時だった。もうひとつの理由は、出かける前にイリヤのところへ寄っていればよかったと思ったからだった。あのロシア人は、たった今役に立つ何かを発明していたかも知れない。
けれど他にも、理由にならない理由があった。彼は単にイリヤのことを考えると心が落ち着いたのだ。それが何故なのかは分からない。ナポレオンはあの男とまだ片手の数ほどしか会話を交わしたことはないが、あのロシア人が気に入っていた。もう相当に。彼の中にある何かが、ナポレオンの中にある何かに響いてくるのだ。
足音が聞こえてきて、ナポレオンは気をよくした。敵が近づいてくるということは、こんな風に縛られている間に少しばかりのケガや暴力を我慢しなければいけないとしても、運がよければ、そしてうまく事を運べば、脱出の手口が掴めるというものだ。
二時間後、彼は銃とコミュニケーターを取り戻し、応援を要請し、新しい化学兵器の製造式を手に入れた。その引き換えにはアバラが一本折れたのと数箇所の外傷ぐらいで、ナポレオンは割に合ったと言う以上の取引きだと考えた。
U.N.C.L.E.本部に戻って、屈んで受付嬢にバッジをつけて貰っていると、彼女はメッセージを取り出した。
「あなたに伝言があるわ、ああこれ。『ドクター・クリヤキンより、面会を乞う』」
どちらにせよナポレオンはラボに製造式を届けに行く用事があったので、これは好都合だった。渡すならイリヤにしようと思っていたのだが、ウェイバリー氏から必ずイリヤの手にのみ渡すようにと言われた時には驚いたものだ。ナポレオンはこの老人が、ロシア人の部下を信頼していることがはっきりと分って嬉しく思った。
不愉快な男の相手をするのが嫌で、ナポレオンはロバートのラボを覗いてからイリヤの部屋に入った。彼はまたしてもカウンターに向かって、顕微鏡を覗いていた。
「僕がここに入ってくる度に君はそいつを覗いてるけど、一体何がそんなに面白いんだい?」
ナポレオンは顔を上げるとナポレオンにニヤっと笑いかけた。
「ちっちゃい裸の女の子が数百人」
ナポレオンは笑いかえした。
「やっぱりそうか」
彼はイリヤに、THRUSHの基地から回収してきた製造式を渡した。
「万が一君がそれに飽きたとしても、こいつがあれば退屈しなくてすむだろ」
イリヤはそれに素早く視線を落とした。
「これを君が持ってくることはウェイバリー氏から聞いてる」
彼は受け取ってパンツのポケットにしまい込んだ。すぐに出て行くこともないと、ナポレオンはカウンターによっかかった。
「ミッシィが、君が僕に用があるって言ってたけど?」
イリヤは頷くと、ナポレオンの脇に手を回して引き出しに手を掛けた。偶然にイリヤが痛めた肋骨に触れて、ナポレオンは思わず顔を顰めてしまった。さっとイリヤが後ろに下がった。
「怪我をしてるのか?」
イリヤが気づいたことに、ナポレオンは嬉しいような困ったような気持ちになった。
「大丈夫さ」
「何があったんだ」
ナポレオンは相手の気遣いを振り払うように首を振ったが、つい返事をしてしまった。
「ちょっとラッキー・パンチを食らっただけだよ」
彼は両手を頭の上に挙げて実演して見せ、肋骨が動いた拍子にまた顔をしかめた。イリヤが眉を寄せた。
「今度も頭の上から?」
今度こそ心配を振り払うように、ナポレオンは片手を振った。
「製造式が手に入ったんだ。All's well that ends well――終わり良しは全て良し、さ」
やや納得したようにイリヤは肩をすくめた。彼は、今度はナポレオンに当たらないよう彼の横に回って引き出しを開いた。ナポレオンは心の中で、さっきイリヤが寄りかかって触れてきた時、自分が何とも思わなかったことをふと考えた。自分のプライベートな空間が侵害されたことなど気にもしなかったのである。
イリヤは目的の物を取り出してきた。腕時計だった。
「ほら」
「ああ、それは必要ないよ」
ナポレオンはイリヤに自分の時計を見せた。
「もう持っているもの」
彼は笑い、イリヤは目を見開た。
「じゃあそっちを外して」
ナポレオンは文句を言った。
「その新しいのはどんな働きをするんだい?」
イリヤが横についている小さなボタンを一度押してみせると、小さいが鋭い鋸目のついた刃が飛び出した。
「これからはロープを切るのに便利になるだろ?」
ナポレオンはイリヤにひねた笑いを向けると、時計を受け取った。イリヤが注意した。
「気をつけて、先が鋭くなってるから」
ナポレオンは頷き、ナイフを元に戻すと自分でイジェクト・ボタンを押した。
「こりゃあ凄いや。他に何か出来るのかい?」
「時間が分かる」
「ふーん」
それからイリヤは時計を取り戻し、文字盤を指差した。
「それと、コンパスにもなる」
彼は口の端を持ち上げた。
「ああ、それに防水仕様になってる」
ナポレオンはイリヤをちらと見ると、時計を取り返してゆっくり向きを変え、真北を向くまで時計を構えていた。
「これは便利だ」
彼はイリヤに満面の笑みを向けると、言った。
「どういう訳か敵はいつも時計は取り上げないんだ。どれだけ長いこと僕をヒドイ目に合わせてるか、思い知らせてやりたいのかもね」
「そんなケガをしないように、どうして君はパートナーと組まないんだ?」
ナポレオンは溜め息をついた。
「組む事にはなってるんだけどね。僕が配属になった時に適当な人間がいなくて、そのまま単独で働くのに慣れてしまった」
イリヤは顕微鏡の脇に戻ると、照明のスイッチをいじった。
「君はそれで何もいわれないのか?」
「ウェイバリー氏からとうの昔に文句は言われ続けてるよ。きっと近いうちに僕はオフィスに呼び出されて、新しいパートナーと引き合わされるだろ」
ナポレオンは不機嫌そうな表情を浮かべた。
「あまり嬉しくなさそうだな」
ナポレオンは髪に手をやりながら言った。
「まともなパートナーと組めるのなら悪くはないけど、もし駄目なやつだったら?そりゃあ、ここにいるエージェントはみなそれなりの人間だが、誰にでも背中を安心して預けられるって気にはならないよ」
彼は自分の指を親指で差した。
「少なくとも、自分が何を考えてるのかはわかる」
イリヤの唇が小さな笑みの形を作った。
「普段は、じゃないの?」
ナポレオンは笑って頷いた。
「時々は自分で自分に驚いたりするね」
彼は新しい時計を着けると、満足げに眺めた。
「またいいものを有難う」
イリヤは肩を竦めた。
「そいつを使うような羽目にならないことを祈ってるけど、どうも君は当たり前のようにトラブルに巻き込まれてるようだから」
ナポレオンは気分を害したようにイリヤを睨んだ。
「おい、その言い方はひどいなあ。幾ら本当のことでも」
そして時計をポケットに滑り込ませた。
「さて、行かなきゃ」
イリヤは顕微鏡を見ながら言った。
「僕はこの製造式を分析しないと」
「昼休みは空けられる?」
イリヤはまたはにかむように微笑んだ。ナポレオンは今度もその笑みに心を奪われ、この場に留まる理由があればいいと思った。しかし見付からなかった。
「じゃあ正午に会おうか。いいかい?」
イリヤは頷いた。これ以上言う事もなくて、ナポレオンは自分の足にドアへ向かえと命令し、やっとのことで言う事を聞かせた。
ナポレオンは気分を鎮めようと頑張ったが、ほんの少ししか成功しなかった。
「ロバート、僕があんたにして欲しいのは、使えるものをくれってことなんだ」
「それなら私は、お前さんが金庫を切断するのにブローランプが必要だというなら、こいつがそのブローランプだと言った筈だ」
彼は問題のブローランプと缶燃料を納めたブリーフケースを指差した。
「だからこいつは大きすぎると言っただろう。目立たないものが入り用なんだ」
「書類カバンより目立たない物に何がある?」
「セキュリティ・チェックで開けて見せなきゃいけない。書類カバンの中にブローランプを入れてる理由をどう説明すればいい?」
「それは私には関係のないことだ、ミスタ・ソロ。私は提供できるものについて説明したし、誰に聞いても同じだろう。もしこれで不都合があるというなら、他の方法を考えるんだな」
ナポレオンは頬の肉を噛み締めた。彼が本当に用があるのはイリヤなのだが、昨日の朝、今回の件について自分に必要な物を相談しにラボへ下りていった時、彼の部屋は鍵がかかっていて、当人の姿はどこにも見当たらなかったのである。
「イリヤはいつ戻ってくるんだ?」
ロバートが彼をじろりとねめつけた。
「私の知ったことか。私がこの部門のチーフで、あのアカ野郎の上司だというだけで何でも知っていると思うのか?
ナポレオンは目付きを厳しくした。
「チビの、何だって?」
「聞こえただろう。変態野郎さ。あのアカにこれでも足りないって言うんなら、うす汚いオカマ野郎だ」
ナポレオンはこの男を殴り付けないよう、努力に努力を要した。
「――ロバート、こういう組織にいる人間として、お前の偏屈さは度を越していると話した筈だ。そいつが目を塞いでいるせいで、お前より遥かに出来た人材なのにそれを評価することすら出来ない」
ロバートは疑り深げな視線を投げた。
「お前さんは奴のところに入り浸りらしいな。それについてはどう説明する?奴がお前さんのために装置を作ってると聞いたが、代わりに何をしてやってるんだ?脳ミソでもくれてやったのか?」
ナポレオンはこれが初めてと言うわけではないが、何故こんな男がまだU.N.C.L.E.で働いていられるのかと不思議に思った。そして今すぐロバートに一発食らわしてやったら、どういう成り行きが待っているだろうかと推測しはじめた。
成り行きがどうなろうと構わないしその価値がある、と思う他になくなった時、突然ロバートのラボの窓の外にイリヤが現れて、こっちに来るよう手招きしているのが目に入った。ナポレオンは一言も言わずにロバートを押し退けると、イリヤについて部屋に入った。
イリヤがドアに鍵を掛けるまで、彼は歓迎の挨拶をするのを待った。
「一体全体どこへ行ってたんだ?僕はずっとあのク
イリヤはにやっと笑った。
「御免よ」
ナポレオンは鼻を鳴らした。
「全然ゴメンと思ってないみたいだけど」
イリヤの目がきらっと光った。
「君にいいものがあるんだ」
イリヤがどんなにわくわくするようなものをくれたとしても、ナポレオンが本当に必要なのは小型のブローランプなのだ。彼は呟いた。
「ブローランプだったらいいのに」
「そうだよ。小型のやつさ」
相手はポケットからペンを取り出すと、それをナポレオンに渡した。彼は手の中のペンに口をあんぐりと開けた。
「これがブローランプだって?」
イリヤが頷いた。彼はペンのキャップを外すと、小さなノズルを引き出した。
「言うまでもないことだけど、これはあまり長時間は使えない。だから二つ作っておいたよ」
彼はもうひとつのペンを取り出した。
「こっちはシャープペンシルになってる」
そのペンを使って、彼は小型のノズルを出し、押して微かなシューっという音がするまでスイッチを押してみせた。ライターの焔をさっと近づけると、ブローランプが点火した。
「これは一つあたり四十五秒しか持たない」
ガスを止めると、ポケットに手を入れインク・カートリッジのように見える小さなチューブを二つ出した。
「ガスのスペア容器もふたつ作ってある」
彼はナポレオンに交換の仕方を見せた。
「僕は四秒ほどしかガスを使ってないから、これで大体二分と五十六秒ぶんは使える計算だ」
ナポレオンは言葉を失った。それから目を細めた。
「有り難くないわけじゃないけど、どうして僕にこれが必要だって分かったんだ?」
「あてずっぽうさ」
ナポレオンは首を振った。
「その手では一度誤魔化されてる。僕が計画書を作ったのは一昨日のことで、オフィスからまだ出してもいないんだ」
イリヤは罪のなさそうな、それも怪しげなような視線を向けた。そして次の一言でまとめて吹き飛ばしてしまった。
「オフィスと言えば、ピッキング道具のいいやつは欲しくない?」
ナポレオンは目を見張った。
「イリヤ、君は僕のオフィスに忍び込んだのか?」
チッチ、とイリヤは舌を鳴らした。
「本気でウェイバリー氏にあのへんのセキュリティを強化してもらった方がいいよ。入るのはばかみたいに簡単だったんだから」
「いや、僕が心配しなきゃいけないのは誰かが僕のオフィスに忍び込んだってことじゃない、特にU.N.C.L.E.の職員なら」
「でも僕が入り込めたのなら、THRUSHだって入り込めたはずだ」
そこでイリヤは躊躇うように顔を横に傾げた。
「まあ、実際にそんなことはなかったとしても、僕が簡単に入り込めたって事実は変らない」
ナポレオンは苛立たしげな吐息をついた。
「あのファイルは最重要機密だったんだ。もし僕がこのことを報告すれば、君は保安課の聴聞会に引っ立てられるぞ」
イリヤが首を振った。
「僕には最重要機密委任認可
ナポレオンはイリヤを凝視した。
「機密委任許可があるって?」
イリヤが頷く。
「何故だ?」
イリヤが肩をそびやかした。
「何か問題があるかい?」
「もし君に委任許可が下りてるなら、どうしてファイルを見るのに僕のオフィスに侵入したんだい。何故普通に見せてくれと言わなかった?」
「それじゃあ面白くないじゃないか」
ナポレオンはちょっとの間、また絶句した。
「――おもしろくないって?」
イリヤが頷き、彼はぶっと噴き出した。
「クリヤキン君、君みたいな奴にはお目にかかったことがないよ!」
そこで眉を寄せた。
「本当に委任許可があるんだな?」
「本当に本当さ。もし信用できないのならウェイバリー氏に確かめてみるといい」
ナポレオンは手の中の小さな装置をじっと見た。
「……それなら、僕が解ったと思うことを確認させてくれ。君は僕が取組んでる事件のファイルを読みに僕のオフィスに侵入した。読んだ後、君は僕と同様、小型のブローランプが必要になるだろうとの結論に達した。それで君は姿を消したのか?僕にそいつを作るために?」
イリヤがクイと顔を上げた。
「そりゃあ、ちょっとばかりコジツケが過ぎるんじゃないか?」
ナポレオンはわけがわからなくなってしまった。自分にここまでのことをしてくれた者は誰もいない。それはまるでナポレオンに任務を成功させて無事に戻ってこさせるのが、イリヤ個人の責任とか務めであるようだった。イリヤが彼の守護天使
ナポレオンは、もし他の者がこんな事をしたのなら、プライバシーを侵害された気がしただろうと思った。けれど何故かイリヤが相手だと、自分の生命がこの上なく頼りになるものの手に守られているのだとしか思えなかった。彼は顔面にゆっくりと笑みを広げた。
「もうどこかへ姿をくらましたりしないって約束してくれるかい?」
眩しいほどの微笑みが返されてくる。
「なるべくそうする」
そして、イリヤは隣のラボを指差した。
「ロバートは何をわめいてたんだ?」
ナポレオンは嘲るように鼻を鳴らした。
「どうやら僕は、君の作ってくれる装置と引き換えにカラダでご奉仕してるらしいんだとさ」
イリヤは目を丸くし、それからナポレオンの手の上にある道具を見下ろした。彼はナポレオンに謎めいた笑みを向けた。
「そういうことなら相当暇がかかるんじゃないかなあ」
ナポレオンは忍び笑い、それからイリヤを見つめながら、ロバートが言ったことを思い出した。少しの間、イリヤは本気で言っているのだろうかと考えた。少しの間、だったらどうなんだろうと考えた。
それから彼は首を振ってその考えを振り払った。イリヤは冗談で言っているに決まっている。ナポレオンはそんなことを考えた自分を恥ずかしく思った。また我ながら突っ込んで考えたいとは思わない何らかの理由で、少しだけ残念な気がした。
イリヤと目を合わせると、ロシア人の瞳にまた別の輝きが宿っているのが見えた。それはまるで、ナポレオンの一巡の思考を追いかけていたようだった。彼はきょとんと目を丸くした。
「僕は今日の午後出発しなきゃならないんだけど、帰ってきたら君に夕食をおごるよ」
そして手の中の小さなブローランプを握り締めた。
「こいつをどうも有難う」
イリヤは何でもないと言うように手を振り、ナポレオンの感謝の言葉を打ち消した。魔法使いのようにソロの願いを叶えるのは、ありふれた毎日の出来事だとばかりに。
「それより無事で戻って来いよ、自分で自分を焼き付けたりしないように」
ナポレオンはさっきイリヤが言った台詞を返した。
「なるべくそうする」
彼は向きを変えて出ようとしたが、ロシア人をうわべだけ睨みつけて言った。
「それと次にはね、ファイルを見せてと頼んでくれりゃいい。分かった?」
イリヤはただ彼を見返すだけだった。ナポレオンは溜め息をつき、別の手を切り出した。
「僕に新型や改良型の装置を薦めてくれるのなら、同じように君が使ったピックをくれてもいいんじゃないか。君がそれで僕のオフィスに侵入できたとすると、僕が持ってるどんな道具よりいいものなんだろう?」
イリヤはポケットから細い針金の切れ端を取りだし、ナポレオンに手渡した。ナポレオンはそれを手に取ると眉を顰めた。
「これがそうなの?これじゃピッキングの道具そのままじゃないか。君のことだからタイピンやタバコに見せかけたのを作ってると期待したのに」
イリヤは機嫌をそこねたような目で睨んだ。
「それはまだ制作途中なんだ」
ナポレオンはにこにこと笑いかけた。
「だと思ったよ、きみ」
ナポレオンはウェイバリー氏のオフィスに向かっていた。リサが彼を招きいれた。
「ウェイバリーさんがお待ちよ、ナポレオン」
ナポレオンは彼女にとびきりの魅力的な微笑を浮かべると、上司のオフィスに入っていった。
「何の用だね、ミスタ・ソロ?」
「イリヤについてお話したいことがあります」
ウェイバリーは鋭い視線を投げかけた。
「彼の出自のことで文句を言うつもりではないだろうね?」
ナポレオンは相当な数の人間が、彼を面白くなく思ってウェイバリー氏のところへ来ているのを知って顔をしかめた。
「いいえ、彼は実に優秀です。これまで彼は幾つも私に、見たこともないほど優れた装置を出してくれました。私の見る限り彼はラボの責任者になってしかるべきだと思います」
ウェイバリー氏はふむ、と頷いた。
「それを聞いて何よりだ。で、君は何が言いたかったのかね。それともその事かね?」
ナポレオンは咳払いをひとつした。
「彼は……彼には最重要機密委任認可が下りているのですか?」
ウェイバリーはパイプを二度ほどふかしながらナポレオンを見た。ナポレオンはそわそわと落ち着かない気分になるのを懸命に我慢した。ウェイバリー氏の凝視を一身に浴びて気の休まるはずがない。
「ああそうだ」
ナポレオンはそれを聞いてほっとしたが、まだ困惑していた。
「理由を伺ってもよろしいですか?」
ウェイバリーはパイプを灰皿に打ちつけた。
「いかん」
ナポレオンは眉を寄せた。
「では何故いけないのか伺っても?」
「それもいかん」
ナポレオンは溜め息をついた。これでは何のことやらわからない。あの男はロバートの下で働いていながら、ウェイバリーの命で動いているらしい。そしてウェイバリーは何も教えてくれない。
まあその事についてはいずれ解るだろう。なんといっても自分はスパイなのだ。
「もう用は済んだかね、ミスタ・ソロ?私にはひとつふたつ目を通さねばならないものがあるのだが」
嫌味を言われてもナポレオンはひるまなかった。
「もう一つだけ。ロバートのことについて聞いていただきたいのです。彼はイリヤに向かって何度も不愉快な発言を繰り返しています。本来仕事仲間を悪く言いたくはないのですが、彼の発言は少々行き過ぎている」
ウェイバリーはパイプに新しいタバコを詰めた。
「うちの新しい掘り出し物についての、ロバートの態度はよくわかっとる」
それでは十分でない。ナポレオンにはイリヤがそのことについて不満を漏らしたりしないことは分っていたし、誰かが止める必要があるのだ。
「貴方から奴に話していただけませんか?」
ウェイバリーの目付きで、ナポレオンは自分の本分をはみ出してしまったのに気づいた。しかし引き下がりはしなかった。ウェイバリーは跳ねつけるように言った。
「君には集中せねばならん任務があった筈だが?」
「……イエス、サー」
ウェイバリーにこれ以上厄介な仕事を押し付けられないよう、ナポレオンは足早にオフィスを出ていった。
一週間が経ったが、ナポレオンには何も判らなかった。人事課に愛想をふりまいて調べてもらっても、そこにイリヤのファイルは無いということが判明しただけだった。その次にナポレオンは、イリヤから貰ったピックを使ってロバートのオフィスに忍び込んだ。鍵のかかったファイル・キャビネットを開き、この男の部下のファイルをみつけ、そこにイリヤの名前も含まれていたのを目にして彼は満足の息をついた。
彼はファイルを取り出し、ロバートの机に座ってそれを読んだ。開いてみると中にはルーズリーフの用紙が入ってるだけで、ナポレオンは眉を顰めた。奇妙に思いながら、彼は最初の一枚を取って読みはじめた。
そこに記されている悪辣な讒言の数々が毒のように染み出してくる気がして、彼は幾らも読まないうちに用紙から手を離した。恐る恐る他のページも覗いてみたが、同じような内容が続いていただけだった。どのページを見てもロバートは、イリヤを口を極めて罵っていた。イリヤはある人物の企みに従って、ニューヨーク、ひいては全組織を乗っ取ろうとしており、その間異常で猥褻な行為をくりかえしていると、あからさまな敵意と疑惑をもって述べられていた。
ナポレオンはファイルを閉じると、拳を固めて唇に押し付けた。どうみてもイリヤに対する考え方は、ロバートが適性を欠いた人間だということをはっきり物語っているとしか思えない。
このファイルをウェイバリー氏に見せるべきではないかと思ったが、そうするにはまず何ゆえにナポレオンがロバートのオフィスに忍び込むことになったのかを説明しなければならない。そしてウェイバリー氏に、イリヤの件については放っておくようにという命令を無視したことを話すのは、あまり褒められたことには思えなかった。
彼はこのファイルをそのままにしておき、そのうちロバートがやり過ぎて自分で自分を縛り上げるような羽目になることを祈った。ナポレオンは立ち上がってファイルを元の場所に差し込むと、キャビネットを施錠し直し、そしてロバートのオフィスを出た。
通路に立ち止まって、彼は次にどこを捜そうかと悩んだ。イリヤのファイルが人事課にも、ロバートの所にもないとすると、考えられるのはウェイバリーのオフィスである。ナポレオンはあの老人の内なる聖地に忍び込もうという考えを抱くほど馬鹿ではない。
彼はロンドン本部に何度か電話をかけてみたが、情報は何も得られなかった。まるでイリヤはU.N.C.L.E.のラボで造られたかのようだった。
そんな風に考えてもナポレオンは愉快にはなれなかった。彼の装置のおかげで、自分はもう何度も任務を成功させてきた。この間の任務など、彼はカスリ傷ひとつ負うことなく戻って来れたのだ。
とはいえ装置だけが問題なのではない。ナポレオンはいつのまにかあの男がますます好きになっていた。地球の両極ほどに違っているにも関わらず、彼と居ると他のどの同僚と一緒にいるより落ち着いた。
彼は謎にいつも付きまとわれているのが気に入らなかった。何故ならイリヤが、そのうち現れた時と同じように突然姿を消してしまうように思えるからで、それで良かろう筈がなかった。
今やイリヤはナポレオンの生活の一部になっている。彼はずっとこのままであって欲しかった。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
